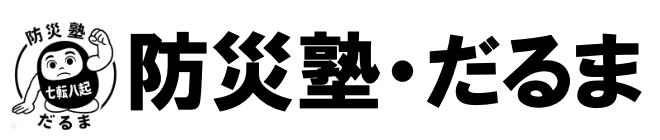― 忘れてはならない教訓と未来への備え

地震への備えの空白を震度7の地震が襲いました。6千人以上の人名が失われましたが、その8割は耐震性の低い家屋の倒壊によるものでした。また、倒壊した家屋のエリアはベルト状になっており、その地盤による増幅が明らかになりました。

ここで地震が起きるとは思わなかった
1995年1月17日、阪神・淡路地域を大地震が襲いました。多くの関西の人々は、「この地域では大地震は起こらない」と考えていましたが、実際には過去にも慶長伏見地震(約400年前)などの大地震が発生しており、関西も地震のリスクを抱えている地域であることが明らかになりました。
備えの空白
被災地では、地盤の弱い地域に耐震性の低い建物が密集しており、これが被害を拡大させる一因となりました。特に、古い木造住宅が多く倒壊し、多数の犠牲者を出しました。このことから、日頃からの耐震補強や建物の安全性確保の重要性が再認識されました。
避難行動や避難所運営の課題
地震発生直後、多くの住民が学校などの避難所に避難しましたが、避難者数が数千人に及び、避難所は溢れかえりました。これにより、物資の不足やプライバシーの確保、衛生環境の悪化など、多くの課題が浮き彫りとなりました。避難所運営の事前準備や地域コミュニティの連携の必要性が強く求められるようになりました。
防災とボランティアの日
阪神・淡路大震災を契機に、1月17日は「防災とボランティアの日」と定められました。震災時、多くのボランティアが被災地で救援・復旧活動に尽力し、その重要性が広く認識されました。これ以降、ボランティア活動は災害対応の重要な柱となり、地域社会の防災力向上に寄与しています。
防災塾・だるまの視察レポート
阪神淡路大震災30周年記念 現地訪問レポート(2025年1月 21日)
第152回レポート 阪神淡路大震災から23年!神戸から学ぶ(2018年2月)
第141回レポート 神戸から学ぶ 災害から22年目(2017年3月)
第116回レポート 阪神淡路大震災から20年・・・「いなむらの火」 (2015年2月)
講演会
第169回レポート 必ず発生すると言われる東海・東南海地震 私たちの命は、生活は守れるか(講師:松山順三氏(元神戸市役所職員、阪神淡路大震災時の須磨区対策本部)
私たちの命、生活を自ら守ろう!~阪神淡路大震災の経験を横浜で役立てよう~(講師:松山順三氏)