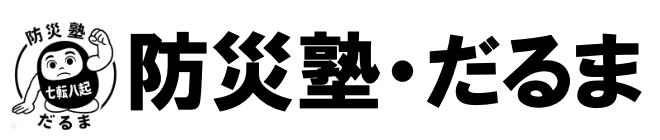防災塾・だるまでは、コロナ禍の2020年度〜2022年度にわたり、災害と防災の探究課題を自助・共助・公助・新時代対応に設定。
当時可能となったリモート会議、サロンごとの協議活動を活用し、探究を深めました。
2022年に発表会を開催し、探究成果と未来の防災に向けた提言を共有しました。
それが2024年度〜2025年度にはそれをベースに会員の意見を結集し、防災長創設への提言に進みました。
🅐 Aサロン:「自助力推進」サロン
提言キーワード:
- 耐震化コーディネーターの育成
- 住宅の耐震診断・補強の普及
- 倒壊家屋からの救出計画策定
- 地区防災計画・地区タイムラインへの耐震化の明記
- 一級建築士との連携と説明責任
- 評点(耐震性能指標)の理解と向上目標設定
🅑 Bサロン:「共助力向上」サロン
提言キーワード:
- 地区タイムライン(OURタイムライン)の作成
- 防災まち歩きと地域訓練の定着
- 自主防災組織の活性化とリーダー依存からの脱却
- 互近助(ご近所共助)の文化づくり
- 防災とBCPの地域連携(企業・福祉・公民館)
- 地区防災計画・タイムラインの法制化推進
- 行政とのPDCA型協働体制の確立
🅒 Cサロン:「自助・共助・公助連携推進」サロン
提言キーワード:
- 地区タイムラインの統合と実効性確保
- 多主体(自治会・学校・福祉・消防)参加型タイムライン
- 大川小・台風19号の教訓から学ぶ連携不足の克服
- IT統合ツールによる防災計画の見える化
- Our Timeline(組織ごとの行動計画)の整合
- 自治体・国交省・内閣府制度の整合と支援の仕組み
- 防災基本計画のタイムライン化
🅓 Dサロン:「時事防災課題探究」サロン
提言キーワード:
- 気候変動・地震・感染症・原発災害の複合リスク対応
- マルチハザード視点での防災教育と政策提言
- 差別・共生・福祉を含む社会包摂型の防災
- 市民のアンテナ力・発信力の強化(防災ジャーナリズム)
- 多分野連携と人的ネットワーク(Know-who)の活用
- 社会的要因を含む“合成の誤謬”への理解と防止
- SDGs視点からの防災まちづくり
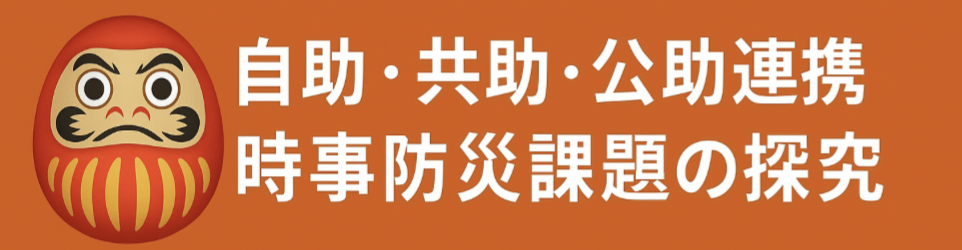
🅐 Aサロン:耐震化による「命を守る備え」の推進
~自助・共助・公助の連携を見据えた地域耐震戦略~
◆ 背景と課題意識
阪神・淡路大震災では、家屋倒壊による圧死・窒息が犠牲者の約6割を占めました。首都直下地震のリスクが現実味を増す中、「ゼロ・アワー前に命を守る備え=住宅の耐震化」の推進が急務であると、Aサロンでは認識しています。
横浜市の耐震化率は91%(2022年時点)ですが、95%を目標としても、実際の地域差や意識の格差が課題として残されています。
◆ 提言1:耐震化コーディネーターの育成と地域配置
- 地域の防災活動家やマンション管理組合の一員が「耐震化コーディネーター」として、相談の窓口や診断の仲介を担う仕組みを提案。
- 専門家(建築士・行政相談窓口)との連携を図り、診断・設計・工事・資金調達までの流れを地域で支援。
キーワード:自助力の強化、専門知見の地域内展開、伴走型支援
◆ 提言2:倒壊家屋からの救出体制を地区計画に組み込む
- 地震発生直後の「初期行動」に備え、地域の自主防災組織や自治会が救出手順を明確化。
- 「地区防災計画」や「地区タイムライン」において、耐震化推進の担当配置や、発災後の救出段取りを明記する仕組みづくりを推進。
キーワード:共助の計画化、要配慮者の早期救出、計画の実効性向上
◆ 補足知見:地震被害と耐震性能の関係(熊本地震を踏まえた考察)
- 耐震基準の違いによる被害率の変化は顕著。S56以前の旧耐震住宅の倒壊・崩壊率は95%近くに達する一方、2000年以降の「新新耐震」基準では**被害率39.9%**にまで低下。
- **住宅性能表示制度による「耐震等級3」**の取得で、ほぼ無被害となるケースが多く、数値目標の明示が重要。
◆ 総括:専門家と連携し、自ら判断する力を
自宅の安全性を他人任せにするのではなく、住民一人ひとりが「希望する耐震性能とリスクの関係性」を理解し、診断士と対話しながら判断する姿勢が求められています。
Aサロンは、「耐震を地域で考える時代」への移行を提案しています。
Bサロン:地域共助力の向上とタイムラインによる災害対応強化
~自助・共助・公助が一体となった防災まちづくりの実践提言~
◆ 背景と課題意識
Bサロンのメンバーは、それぞれの地域で自治会や防災組織のリーダー・実践者として活動しています。地域の地形特性や住民構成に即した「リアルな防災行動モデル」を提案し、マイタイムラインや地区防災計画の策定・訓練実施までを視野に入れた“共助の現場力”を追求しています。
◆ 活動の柱と具体的取り組み
1. 地域タイムラインの整備と住民参加
- 「マイタイムライン」から「互近助(ごきんじょ)タイムライン」へ
- 地区単位の避難行動計画(OURタイムライン)を住民とともに作成
- 平塚・葉山では、防災まち歩きから避難訓練へと一体的な展開
2. 防災まちづくりの組織化
- 自主防災会の設立・活性化を推進し、リーダーに依存しすぎない共助体制を確立
- QQ防災クラブ(秦野市)の取り組みをモデルに「仕組みで守る防災」を実践
◆ 各レベルへの提言
▶ 地域・住民への提言
- 「マイタイムライン」作成から始める防災意識の普及
- ご近所で助け合う“互近助”文化の定着
- 防災まち歩きと訓練を通じた日常化と継続化
▶ 行政への提言
- 防災基本計画の「タイムライン」項目を実質化し、PDCAで運用強化
- 行政主導でなく、地区タイムラインを整合・支援する体制づくり(足立区など先進事例あり)
▶ 福祉・地域施設・事業者への提言
- 社協・公民館を拠点に住民巻き込み型の防災事業の展開
- 地元事業者とのBCP連携と地区タイムラインの整合
- 消防法・水防法・条例を活かした責務明文化と実践支援
▶ 国への政策提言
- 地区防災計画(内閣府)とタイムライン(国交省)の整合推進
- 「地区防災計画+地区タイムライン」作成支援の法制化
- 実情に即した防災地区(生活圏・流域等)の制度化義務化
◆ 総括:防災の行動計画を“面”でひろげる
Bサロンは、住民目線からの実践的な共助体制と、行政・事業者・福祉との協働モデルを提示しています。災害は“点”ではなく“面”で対応すべきという視点のもと、地区単位での連携型タイムラインとその制度化こそが、命を守る防災社会の基盤となると提言しています。
Cサロン:地区タイムラインの実践と統合による防災連携の突破
~東日本大震災・台風19号の教訓から導く、共通行動計画の再構築~
◆ 課題意識と目的
Cサロンは、地域における「自助・共助・公助」の役割が分断・混在している現実に対して、これらを**統合的に結び直す“実効的な防災まちづくり”**の推進を目的としています。自治会・学校・消防団・福祉関係者など多様な主体が、**連携可能な共通の行動計画(タイムライン)**を共有できる地区防災の仕組みを検討してきました。
◆ 主な活動とテーマ(2021〜2022年度)
1. 大川小学校津波事故の検証
- 「学校と地域・行政との避難計画協議不足」が被害拡大の一因(仙台高裁判決)
- タイムライン未整備により教員・区長・地域住民の避難判断に整合性なし
- 判決が指摘した「校長の法的責務」はタイムライン構築の根拠となる
2. 台風19号(2019年)の多摩川・鶴見川水害分析
- 行政からの警告があったにもかかわらず、住民行動がバラバラ
- 「マイタイムライン」だけでは不十分で、「地区タイムライン」の整備が不可欠と認識
3. タイムラインの再定義と制度的整合
- 国交省が定義する「行政タイムライン(GTL)」と「地区タイムライン(CTL)」の区別と連携
- 足立区などの先進事例から、行政と住民が協働する「コミュニティ・タイムライン」の必要性を確認
◆ 実践的成果とツール開発
- 大倉山連合町会において、多主体(自治会・学校・福祉・消防団等)によるリアルタイム協議で“統合型地区タイムライン”を構築
- 高齢者も対応可能なGoogleフォーム形式のITツールを開発し、従来の紙・付箋型WSよりも効率的かつ即時データ化が可能
- 「気づき→参画→行動→減災」の循環を生む“参加型タイムライン教育”の有効性を確認
◆ 各主体への提言
▶ 家庭・個人への提言
- マイタイムラインの前に地区タイムラインの共有を(判断の前提として)
- 公助TL → 共助TL → 自助TL+業助TL の順に学び、つなげる
▶ 地域への提言
- 地域ごとのマルチハザードに応じたタイムライン統合
- 地区主体が各自の「Our Timeline」を持ち寄り、共通化(CTL)するワークショップの実施
▶ 自治体への提言
- 防災基本計画の改訂に基づく「行政TLと地区TLの整合化」支援
- 自治体主導ではなく「支援型」でのタイムライン構築サポート(事例:二宮町)
▶ 国・制度への提言
- 内閣府(地区防災計画)と国交省(TLガイドライン)の制度的整合と法制化
- 「気候非常事態宣言」の踏まえた制度変革の提起
◆ 総括:防災行動を“見える化”し、つながる力に
Cサロンは、「それぞれの組織がバラバラに動くのではなく、事前に“見える形”で統一されたタイムラインを持つこと」が、命を守る最前線であると提唱します。そのためのIT統合ツールの開発と地域実践を通じて、住民参加型・統合型の防災計画モデルを示しました。
🅓 Dサロン:変化する社会と複合災害に備えるために
~時事性・多様性・複合性に対応する防災課題の探究~
◆ 目的と視座
Dサロンは、「自助・共助・公助」の枠組みにとらわれず、現在進行形の災害・社会的危機を多面的に捉え、防災の新たな地平を切り拓くことを目的としています。
自然災害だけでなく、感染症、差別、福祉、地政学的リスクなども含む“複合的リスク”を扱い、「今起きていること」に対して敏感にアンテナを張り、行動・発信していく市民の役割を重視しています。
◆ 主な活動とテーマ(2021~2022年度)
◎ 取り上げたテーマ例
- 気候変動(温暖化と豪雨・台風の巨大化)
- 地殻変動(地震・火山)
- 感染症(パンデミック)
- 差別(人種・ジェンダー)
- 少子高齢化と福祉
- 原子力災害・エネルギー安全保障
- CBRNE災害(化学・生物・放射性物質・核・爆発)
◎ 具体的な活動
- 第185回談義の会(2022年):豪雨と河川氾濫をSDGsの視点から検討。流域治水の住民参加型行動「水マス(私でもできる)」を紹介。
- フィールドワーク:横浜市緑区白山の崖崩れ現地での見学+勉強会。
- 第190回談義の会(2023年予定):JAMSTEC研究員を招き、「海洋温度上昇と気象災害(台風・豪雨)」をテーマに講演予定。
- 戦災と震災の比較学習:過去の災禍を歴史的に検証し、教訓を導出。
◆ 提言と今後の方向性
1. マルチハザード対応の視座を持つ
- 防災教育・地域活動において、CBRNE災害、感染症、戦争・原発リスクなども視野に。
- 単一の災害対応ではなく「複合災害モデル」への理解促進。
2. 社会的要因を含めた災害分析
- 災害の“原因”を自然科学に限定せず、「人間の選択・制度設計」も含めて多面的に分析。
- 「合成の誤謬」(個々は正しくても全体として誤る)を避けるリスク認知教育の導入。
3. 発信する市民、つながるネットワーク
- 毎日の出来事に敏感な“市民防災ジャーナリスト”としての意識。
- 「Know-who」=誰とつながるか、を重視した人的ネットワークづくり。
- 情報共有の仕組みとして、地域内外との定期的な対話・勉強会を提案。
◆ 総括
Dサロンは、「災害」とは自然現象に限らないという立場から、現代社会の構造的脆弱性と向き合い、防災を“社会を問い直す視座”として位置づける活動を続けています。