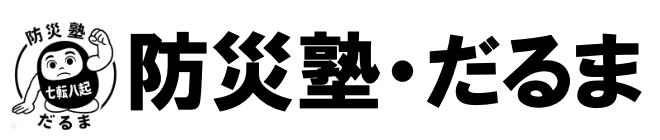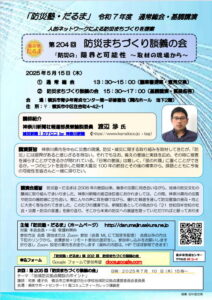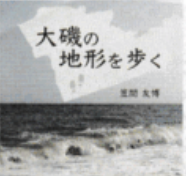NEW! 第205回防災まちづくり談義の会 「避難所運営の初動体制はできていますか?」 和泉禮子氏 開催報告
日時:2025年7月10日(木)15:00~17:00
会場:県民サポートセンター11階の講義室1 参加:20名(会場+Zoom)
テーマ「避難所運営の初動体制はできていますか?」
講師: 和泉禮子氏
横浜市立東希望が丘小学校地域防災拠点委員会委員長
プロフィール:地域防災拠点活動に携わって20年余り。『防災拠点ニュース』の編集長として各自治会町内会及び小中学校を取材。被災地取材を積極的に行って避難所訓練に反映している。



講演要旨
円滑な避難所運営は、初動時即ち「避難所開設」の体制がしっかりと構築されているか否かがポイントになります。避難所開設から運営への移行、その班編成や人員配置についてお話させて頂きます。(和泉禮子)



開催趣旨:
「地域防災拠点」は災害対策基本法における「指定避難所」であるが、横浜市震災対策条例では、それに加えて「情報の受伝達を行うための拠点及び防災用の資材、機材等の備蓄場所として整備するもの」「(市が支援し)地域の住民、職員等からなる地域防災拠点運営委員会が運営する」という高度な機能を位置づけられている点では、先進的な取り組みである。単なる避難所だけでなく、公助と共助が連携した、災害時の本部としての機能が期待されている。横浜市では全市的に地域防災拠点訓練を中心にした地区防災の強化が図られているが、旭区東希望が丘小地域防災拠点の取り組みは広く注目されている。その地域防災拠点委員会委員長である和泉禮子氏が本会にご入会いただいたことは心強い限りである。そこで、早速本年度の談義の会としてご講演をお願いした。(塾長)
講師:和泉禮子氏について
講師:和泉禮子氏について(修正版)
和泉禮子氏は、横浜市旭区の東希望が丘小学校地域防災拠点運営委員会の委員長として、地域防災の推進に尽力されています。2004年に自身が住んでいる新興住宅地管理組合で防災訓練が行われていないことに危機感を抱き、委員会に参加。以来、長年にわたり防災訓練の実施や情報発信を強化し、地域の防災力向上に貢献してきました。
特に、避難所における女性や子どもへの暴力・暴言を防ぐための巡回組織の設置や、炊き出し作業の性別による役割分担の見直しなど、ジェンダー平等の視点を取り入れた防災対策を推進。また、避難所での生理用品の配布方法についても、複数の配布方法を提案し、避難者の尊厳を守る取り組みを行っています。
これらの先駆的な活動が評価され、2024年度の横浜市男女共同参画貢献表彰の功労賞を受賞しました。和泉氏は「女性の視点を取り入れて運営してきた。気づきが大事だと思っている」と述べています。
さらに、和泉氏は横浜市主催の地域防災拠点運営研修で講師を務め、避難所開設時の重要性や運営への移行のポイントについて、実体験に基づく講話を行っています。「避難者をお客様扱いはしません」という言葉には、避難所運営における共助の精神が込められています。(塾長)
参考:タウンニュース他

🧱 講演レポート 地域防災拠点訓練の工夫と実践ポイント
(和泉禮子氏プレゼンテーションに基づく)
🟦 1. 訓練の基本方針:「本番さながらに」
- 避難所訓練は通常の防災訓練とは異なることを明確化。
- 一般の防災訓練=初期消火・AED・炊き出し等
- 避難所訓練=建物安全確認、受付対応、居住区設営、資機材起動、健康管理など
- 「今この瞬間に地震が起きたら…」を想定し、仮想ではなく実地行動を重視 。
🟦 2. 仮組織3班制による初動体制の明確化
【工夫】
- 避難所開設初動に即応するため、事前に3班体制を設計:
- 🟩 建物・ライフライン安全確認班
- 🟥 居住区設営班
- 🟨 避難者受付・健康チェック・情報収集班
- 委員長直轄事務局から各班に指示が届く体制を整備 。
【効果】
- 訓練当日は仮組織に即分担され、各班が役割を即座に遂行。
- 安全確認は指差呼称・様式使用によって実効性と記録性を確保 。
🟦 3. 開設マニュアルの文字化・視覚化
【工夫】
- 発災直後に必要な物資・手順をすべて文字化。
- マニュアルにはイラストやフロー図を挿入し、初めて見る人でも理解できるよう工夫。
- 毎年訓練で使用→検証・修正を重ねるPDCAが確立 。
🟦 4. タイムラインによる段階的運営計画
- 避難所開設から閉鎖までを「4期」に分類:
- 初動期(発災直後~24時間)
- 展開期(2~4日目)
- 運営期(5日目以降)
- 撤収期(閉鎖と学校返還)
- 各段階での責任者・主活動内容を明示し、混乱を防止 。
🟦 5. トランシーバー・デジタル無線・特定小電力トランシーバーの活用
- 防災拠点に配備されているデジタル移動無線機、アマチュア無線機の活用
- 第3の通信手段として特定小電力トランシーバーの活用を推進
🟦 6. 人材確保への工夫と仕組み
【工夫】
- 自治会会長以外の人材にも運営委員参加を要請(マンション・未加入団体含む)。
- 若年層・未経験者の登用 → 新しい発想と継続力に期待。
- 運営委員の中に継続的に活動する役員会を設置 。
🟦 7. 女性の視点・ペット同伴避難など現場目線の改善
- 女性の安全確保・生活ニーズに配慮した避難区画・トイレ設置計画。
- ペット同伴避難についても実践的対応を模索。
- 中学校との連携の難しさにも直面し、小学校との連携強化が鍵となっている。
🟨 むすびに代えて
和泉氏は、「避難所運営は初動体制が要」「訓練は本番さながらに」という2つの柱を繰り返し強調し、長寿社会の力を地域防災へ生かす決意を語られました。
被災地の現実に向き合い、そこから導かれる実践知を避難所運営に活かしていく姿勢に、改めて深い感銘を受けました。
また、毎年の経験と試行錯誤を重ねながら改善を積み重ねてこられた多くの工夫の数々には、敬意の念を禁じ得ません。
現場に根ざした知恵と、人へのまなざしの温かさが随所に感じられるご講演内容は、今後の地域防災のあり方を再考する大きな指針となりました。(塾長 鷲山龍太郎)