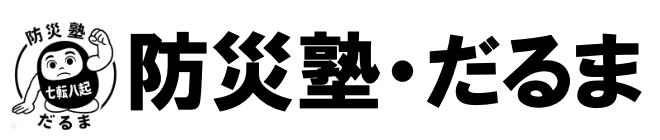第202回 防災まちづくり談義の会 開催報告 「防災まちづくり談義の会」200回を踏まえた防災庁創設への市民提言を考える
第202回 防災まちづくり談義の会 開催報告
〜防災庁創設に向けて、市民と行政の対話を深める一歩に〜
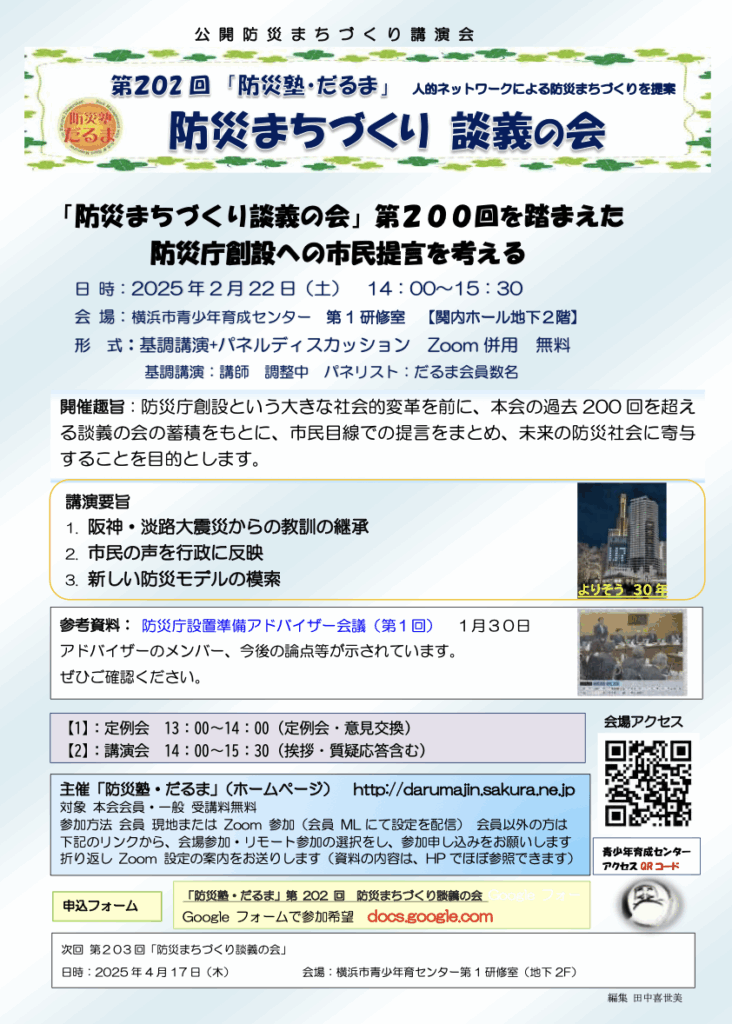
日時:2025年2月22日(土)14:00〜15:30
会場:横浜市青少年育成センター(関内ホール地下)
来賓:古川直季 衆議院議員(総務大臣政務官)
秘書・大屋敷様
発表者:防災塾・だるま会員有志
主催:防災塾・だるま
参加者:21名

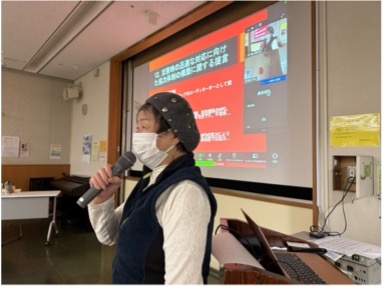

市民の思いを制度へ―防災まちづくり談義の会200回の歩みの先に
防災塾・だるまでは、これまで延べ200回にわたり、市民主体の防災講演会を継続してきました。第202回となる今回は、政府が本格的に動き出した「防災庁」創設の流れを受け、市民による提言を議論する場として開催しました。
冒頭では塾長・鷲山龍太郎より、防災庁創設の準備が総務省を中心に進行していること、災害対策基本法の改正が焦点となっていること、そして「地区防災計画」など制度の隙間にある市民ニーズが、今後の制度設計に反映されるべきであることなどが語られました。
来賓・大屋敷秘書の発言―制度化に向けた「市民の現実的視点」の意義
今回の会合で最も注目されたのは、古川直季議員の代理として出席された大屋敷秘書によるご挨拶と応答です。
「防災庁の創設は、単なる新組織の立ち上げではなく、市民・自治体・企業が一体となってリスクに備える国の在り方を問い直す試みです。200回に及ぶ市民の積み重ねから生まれた提言には、極めて大きな意味があります」
大屋敷秘書はこのように述べたうえで、政務官・古川議員の意向として、「現場を知る人の声を、いかに具体的な制度へとつなげていくかが、防災庁設計の核心である」との考えを紹介しました。
さらに「制度設計はまさに今、検討の途上にあります。皆さまからのご意見は制度を動かす力になり得ます。今後も継続的な連携をお願いしたい」とのメッセージは、参加者にとって大きな励みとなりました。
会員提言の数々――防災庁に求められる役割とは? 事前アンケートによって寄せられた提言からは、切実な現場感覚と制度化への期待が浮き彫りになりました。
・木造建築の耐震化強化(田中氏):「1981年以前の旧耐震基準の建物は命を奪う。2040年には築60年に達する。防災庁が率先して全数調査と改修支援を主導してほしい」
・インフラの老朽化に対する点検制度の確立(樋口氏):「地下構造物は見えない脅威。国が主導する点検と整備制度が必要」
・防災と福祉の統合政策(田中氏):「避難所での福祉対応を制度化し、全国的な整備を進めるべき」
・地域と教育現場の連携推進(山田氏):「防災教育は学校だけでは限界がある。自治体や地域と連携したモデル構築を防災庁が制度化すべき」
生活環境・避難所運営に関する提言
参加者からは、避難所での生活環境改善の必要性、ソフィア基準の導入、プライバシー確保、生活用水の確保など、実体験に基づいた現実的な提言がありました。
地域防災力の強化と人材育成(和泉氏・鷲山氏)
学校教育を含めた防災学習の充実、自治会と学校の連携強化、若年層への啓発など、地域の持続的な防災力の向上について議論されました。
関連死対策と耐震基準への対応(稲垣氏)
災害関連死の予防や2000年基準未満建物への補助制度、防災センター設置による都市型モデルの必要性が具体的に提起されました。
まとめと今後の展望
古川直季議員が政務官として防災庁創設を牽引されていること、また秘書様を通じて今回の会合に誠実にご対応いただいたことに、心より感謝申し上げます。
防災塾・だるまとしては、今回寄せられた提言を整理・集約し、政策提言書として防災庁設置準備室に提出する予定です。今後は、横浜市や他自治体との連携、教育現場での実践とも統合しながら、防災塾・だるまとしての「市民提言」として取りまとめてまいります。
提言書提出に向けた今後の行動計画
・荏本名誉塾長より、鷲山塾長と大屋敷秘書の対話を受けて勉強会の開催を提案
・3月に臨時集会を開催(※後日、3月22日に実施)
・4月17日の定例会にて、提言書の決議を予定
・その後、高橋のりみ市議および大屋敷秘書を通じて古川直季議員へ提言を提出する方針
(記録作成:鷲山)
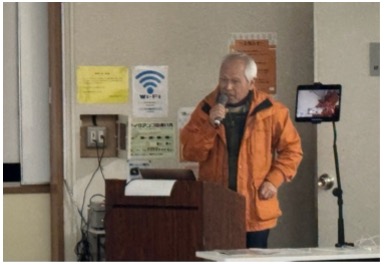


(資料)その他の会員からの市民提言 要約一覧(抜粋)
※防災塾・だるま会員からの提言一覧はHPに公開しています
- 地震で倒壊等殺傷をする木造建物対応に着手
1981年以前の旧耐震建物を全数調査し、粘り強く再建しやすい構造の設計導入を。災害時の死亡事故を防ぐため、要支援者の住環境から対応を始める必要がある。
- 道路陥没など予期せぬ災害(人災)を防ぐために
地下インフラの老朽化対策を、防災庁の主導により制度化すべき。ガス検知器の設置など現場知見に基づく安全設計の観点から、内水氾濫や地下災害も視野に入れて対策する必要性を訴える。
- 防災と福祉の接点部分の相互融合
避難所や災害時福祉対応の制度整備を提案。市民の自助・共助理解を促進し、福祉と防災を分断せず、人権尊重と地域協働による融合が必要。
- 防災まちづくりと人材育成の視点で構築は必要
国の「ふるさと防災職員」制度は人数・任期ともに不十分。熱意ある市民活動団体との連携や地域訓練主導の必要性があり、防災庁が主導すべき。
- ボランティアへの支援
震災直後に動く市民や専門職を支援対象に加え、申請制度と有給支援の制度化を。人命に関わる活動へ国家的支援体制を求める。
- 「危機管理」を教育体系に入れる
災害・犯罪・格差などの危機に対し、生き抜く判断力を教育の中で養成すべき。防災は人間力の教育と不可分である。
7. 防災活動の統合デジタル処理
防災と福祉を統合的に扱うAI・ICTシステムの整備が必要。高齢者を含む全市民が等しく使える仕組みに。