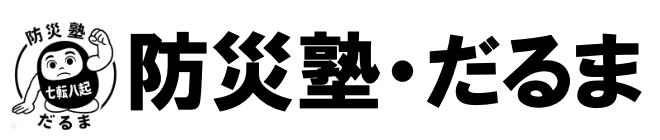ぼうさいこくたい2023 オリジナルセッション神奈川Os-7 講演要旨・資料一覧
-1024x744.jpeg)


ぼうさいこくたい2023 オリジナルセッション神奈川Os-7 講演要旨・資料一覧0914
| 2023年9月17日(日) 会場:横浜国立大学 教育学部棟6号館101講義室 | ||||
| 大会テーマ: 次の100年への備え〜過去に学び、次世代へつなぐ〜 | ||||
| Os-7テーマ: 神奈川の関東大震災から100年の教訓を未来につなぐ | ||||
| ZS1 | オープニングセッション(中継) | |||
| K01 | 開会挨拶 | かながわ人と智ネット代表・神奈川大学名誉教授 荏本孝久 | ||
| 第Ⅰ部 神奈川の関東大震災 発生メカニズム及び被害と減災行動 12:30〜14:30 | ||||
| No. | 主題 | 発表者 | 講演要旨 | 資料・リンク |
| S11 | 関東大震災を引き起こした神奈川の大地と地質「丹沢の谷にサンゴの化石」(海変じて山となる大変動は今も……) | 神奈川地学会 門田真人 | 富士・箱根・伊豆国立公園と「丹沢・大山国定公園」はフィリピン海プレートが生んだ大地です。 丹沢山地と伊豆半島をつくっている地層は海底火山が永い時代活動していた証拠の枕状溶岩、凝灰岩が厚く堆積しています。 その中に点在する石灰岩からは熱帯のサンゴ礁の生物化石が見つかりました。現在の地球上においてはフィリピン周辺のサンゴ礁に相当します。 もとは南の海の火山島であった大地が今は神奈川の屋根です。そして今もこのプレートは移動の活動を止めていません。 次の大きな地震と火山活動が来る前に防災力を…、 | ・書籍「丹沢の化石サンゴ礁」文化堂印刷 2002年 ・論文「丹沢山地より産出する中新世八放サンゴ亜綱アオサンゴ化石について」 東海大学海洋紀要 2005年 ・ビデオ「丹沢の化石サンゴ礁」 (全国自作視聴覚教材コンクール優秀賞受賞) |
| S12 | 未公開空撮写真で見る神奈川の関東大震災 | ジオ神奈川 蟹江康光 | 横須賀海軍航空隊のF-5式水上飛行艇7号機で9月9日撮影の36枚を掲載した.撮影範囲は相模湾の下田~三崎~浦賀~走水までと,館山北条の2枚. 一方,横須賀~追浜,品川~東京停車場の10枚は,佐世保海軍航空隊の航空母艦「若宮」搭載のD式水上飛行艇での撮影は9月5, 6,7, 9日.東京湾南西部の撮影は,9月3日と5 日に所澤陸軍第五飛行隊の飛行船15枚で,横須賀海軍航空隊の報告書では酒匂川橋梁を馬入川(相模川河口)と誤記されていた.これらの写真類は,大日本帝国で,はじめての大災害を軍事機密として記録したものであるが,資料的価値は,関東大震災100年を経て高く評価されるべきであろう. | 蟹江康光 編著, 「関東大震災—未公開空撮写真」 神奈川は被災だった.161 pp.ジオ神奈川2016年刊行 ジオ神奈川ホームページ http://okinaebis.com ぼうさいこくたい2023P-71 空から見る関東大震災 主催団体: ジオ神奈川 https://bosai-kokutai.jp/2023/p-71/ |
| S13 | 複合災害としての関東大震災~地盤災害と同時多発火災~ | 神奈川地学会 相原延光 | 1923年関東大震災は,地震災害直後に火災により多数の人命が失われた複合災害である。まず地震災害の素因となった地盤条件(盛土や埋土)による地盤災害の例を示し,次に気象災害の素因となった気象条件(観測状況と観測記録)について紹介する。地震災害は陥没による低い土地への浸水と歩行困難道路の実態,気象災害は東京陸軍被服廠跡の火災旋風と横浜公園周辺の環境を比較して,災害イメージの紹介をもとに,災害の教訓を示す。 | 所属団体HP: 防災塾だるまHP 談義の会2023年5月チラシ及び記録 文献:相原延光.地盤工学会災害調査論文報告集.1巻2号.pp.198-211.1923年関東地震前後の気象状況-地盤災害,火災旋風の災害誘因の考察のための情報 |
| S14 | 横濱市の関東大震災-救出・消火、そして避難-生死を分けた要因 | 防災&情報研究所 髙梨成子 | 1923年関東大震災最大の被災地神奈川県では、建物や構造物崩壊、地滑りや土石流、津波、市街地大火・火災旋風、危険物施設火災等、近代の災害で発生しうる様々な事象が発生していた。日本で近年発生した都市直下地震で震害と大火に襲われた1995年阪神・淡路大震災と、東京市及び旧横浜市の関東大震災時における被害と対応を比較しつつ、横濱市内において人々が行った救出や消火活動、大火からの避難行動に焦点を当てて述べる。 | 関連発表論文等 ・日本火災学会講演討論会「関東大震災と,以後100年間の火災科学 将来の都市型複合災害に向けた課題を抽出する」における「横浜市の関東大震災の大火と避難にかかる課題」講演、令和5年1月開催 ・「横濱市の関東大震災の大火と避難にかかる課題」、火災誌385号(2023年8月発行)、日本火災学会 ・「関東大震災時の横濱市:災害時ユートピアの出現と消滅―救出・消火活動における共助とその限界-」、機関誌「建築防災」令和5年9月号 ・「関東大震災から100年 横濱市の関東大震災-大火と救出・消火・避難-」、消防庁消防大学校、機関誌「消防研修」 ・日本消防設備安全センター、月刊フェスク令和5年11月号掲載予定 |
| ○司会・コメンテーター: | 神奈川大学名誉教授 荏本孝久 | |||
| 第Ⅱ部 もし、関東大震災が再来したら 14:40~16:20 | ||||
| S21 | 大正型関東大震災の神奈川県シナリオ型地震被害想定 | 神奈川県建設業協会 杉原英和 | 神奈川県が大正型関東地震の被害想定を実施した経過を報告します。また、これまでの被害想定調査の内容を概観するとともに、最新の被害想定調査ではシナリオ型地震被害想定を実施しており、その特徴などを報告させていただきます。 | 神奈川県温泉地学研究所観測だより,第 62 号,2012. 都道府県における想定地震に関するアンケート調査結果について 杉原英和(神奈川県温泉地学研究所) 神奈川県温泉地学研究所観測だより,第 60 号,2010. 市民向け防災教室(図上演習)の効果について 杉原英和(神奈川県温泉地学研究所) 中国・遼寧省地震局訪問記 杉原英和 伊東 博 |
| S22 | 次の震災被害を想定する地盤調査 | 神奈川大学名誉教授 荏本孝久 | 地震による建物の被害には地盤が硬質か軟質かに関係する。このような地盤の硬軟は一般には地形・地質図が基本となるが、近年では建物の建設時のボ-リング資料が有用なデ-タとなっている。しかしながらボ-リンク資料は種々の制約があって地域的な防災対策に利用するためには不十分である。ここでは常時微動というデ-タを利用することで震災被害を想定する地盤調査について、長らく当研究室で蓄積した調査結果を紹介する。 | T. Ochiai et al, “Creation of a New Hazard Map Reflecting the Local Ground Characteristics”, 16ECEE, 2018. 上野直洋他, “GIS による横浜市高密度微動観測結果の卓越周期分布の整理・検討, 第13回地震工学シンポジウム, 2018. T. Ochiai et al, “Study of predominant periods distribution by microtremor observations in Yokohama City of Japan using GIS”, JGIS, 2019. テーマ:市民と共に七転び八起 ~正しく恐れて賢く生きる~ (荏本孝久先生 塾長退任記念講演) |
| S23 | 建築時期別木造住宅の被害状況と住宅耐震性能・耐震改修について | (一社)神奈川県建築士会 防災・災害対策委員会 河原典子 | ご自宅の「耐震診断」「耐震改修工事」について基本的なこと、考えていただきたいポイントを伝えます。熊本地震における「木造の建築時期別の被害状況」調査結果から、「2000年以降」の新築建物の61%が無被害であり、住宅性能表示制度の耐震等級3(耐震基準x約1.5倍)の木造住宅は大部分が無被害であったという事実から、ご自宅の耐震化のご検討をお願いします。 ご自宅の耐震化が一番の「防災まちづくり」になります。 | 一般社団法人神奈川県建築士会 【防災・災害対策委員会】 【防災塾・だるま×神奈川大学連携講座】 「マルチハザード社会を生き抜く防災まちづくり講座」 |
| S24 | 大震災後の生活再建のために | 神奈川県大規模災害対策士業連絡協議会 弁護士 伊東克宏 | 1 被災者が活用できる様々な公的支援制度 2 多様性と複雑さ~組合せが可能なこと 3 正確な知識と将来を見据えた判断 4 運用の違いと変更の可能性~継続的な情報収集の必要 5 専門士業による被災者相談の役割~情報弱者を無くすこと 6 情報収集から運用変更や法律改正へ~被災者相談の機能 | 神奈川県大規模災害対策士業連絡協議会 (kanagawa-saigai.net) https://www.kanagawa-saigai.net |
| S25 | 地震災害発生時の停電による被害と影響 | 神奈川大学教授 朱牟田善治 | 関東大震災から100年が経過した現在でも、都市機能を維持するうえで必要不可欠な電力ライフラインは、激甚化する災害の影響を受ける。近年では、2011年東日本大震災や2018年北海道胆振東部地震などを例として、停電が広範囲に及ぶケースが発生している。本講演では、北海道胆振東部地震でのブラックアウトの事例などを紹介しながら、大変革期にある電力ライフラインのいまの課題を紹介し、停電被害を少なくするための方策について議論する。 | 研究紹介 電力中央研究所報告書 |
| S26 | ※宣伝コーナー | プログラムのリンク紹介・希望者 | (101以外で開催している関連団体イベント紹介) | |
| ○司会・コメンテーター: | 神奈川県建設業協会 杉原英和 | |||
| 第Ⅲ部 過去の災害教訓を今、未来に語り継ぐ 16:30〜18:00 | ||||
| S31 | 関東大震災の被災地を歩く/関東大震災の震源域の遺構から学ぶ防災 | 防災塾・だるま、神奈川地学会 相原延光 | 関東大震災が複合災害であることを念頭に震災遺構を巡る。初心者向きの低地災害体験コースと距離の長い経験者向きの低地・台地災害体験コースが考えられるが,講演では関内コースを例に中心に,横浜の地名由来の道と発展を支えた道を基軸に置き,道の標高データ,地盤構造を理解した上で歩く。地盤災害記録や火災の記録(時刻,行動方向,周辺の環境)などを話題とし,最終的に防災まち歩きコーディネータ養成を目指す。 | 神奈川地学会HP http://es-kanagawa.com/2022/index.html |
| S32 | 平塚〜湘南の関東大震災被害を語り継ぐ | ひらつか防災まちづくりの会 山田美智子 | 関東大震災の震源地の神奈川県では3万3千人死者、行方不明者。湘南の平塚市でも被害が甚大で467名の犠牲者がでました。「ひらつか防災まちづくりの会」では被害を後世に伝える慰霊碑巡りを市民の皆さんと繰り返し行い、なぜこれだけの被害がでたのか自然災害伝承碑として登録されたのかなど地形からのリスクや当時の環境、歴史からも考察してその教訓をいかした対策を一緒に考える活動をしていますのでご紹介します。 | 「ひらつか防災まちづくりの会」HP |
| S33 | 学校を拠点にした防災まちづくり | 横浜市立太尾小学校区 校長 館 雅之 | 地域防災拠点である太尾小学校において、新型コロナウイルスの影響を受けつつ、地域と学校がどのように連携し、子どもたちの成長と安全を促進できるかについて考察します。 特に、子どもたちは地域、保護者、学校が連携した環境で育ち、防災まちづくりに真剣に取り組む大人たちの模範を見て成長し、さらに自分たちで防災について調べたことや日頃の学習で学んだことを発信することへと発展している。さらに、これまでの取組を振り返り、今後の課題と改善点、そして地域と学校が連携を深化させるための戦略や方針について考えていきたい。 | 横浜市立太尾小学校HP |
| S34 | 学校運営協議会で連携する防災まちづくり | 横浜市立北綱島小学校区 北綱島小地域防災拠点運営員会 副会長 垣中祐二 横浜市立北綱島小学校 校長 月橋準弥 主幹教諭 平原広大 | 横浜市立北綱島小学校区は、市の北東の港北区にあり、人口は約8,500名、8つの町内会で組織している。 学校運営協議会は、2010年に発足し、そのメンバーほぼ地域防災拠点運営委員会のメンバーで、学校の安全防災教育と連携・協働している。 学校は、「生活科・総合的な学習の時間」で、防災に関する独自のカリキュラムを作成し、こどもたちは、6年間学習を積み上げ、防災リーダーとして卒業していく。 学校運営協議会で連携する本地域の自助・共助の構築を目指したまちづくりについてまとめた。 | 資料:学校運営協議会で連携する防災まちづくり http://mirai-bousai.net/s34.pdf 「防災塾・だるま」垣中祐二氏講演2021年 「境目のない自助・共助の構築を目指して」 ~被害者 0 に向かって進める自助・共助・公助・医療との連携~ 北綱島小学校区「水害・土砂災害の避難について」 |
| S35 | 北網島小学校における防災支援活動 | 神奈川大学助教 落合努 | 横浜市の北綱島小学校の防災活動支援として、神奈川大学の朱牟田・落合研と島崎・白井研などで協力して子供たちと防災WSを開始している。2022年は、自助+共助を学ぶことを目的に、「防災クイズ」、「紙ぶるるの体験」、「体育館での人力加振体験」を行った。2023年の9月にも「学校内での危険発見」、「避難所で何ができる」といった内容で実施を予定しています。2022年は4年生、2023年は5年生とつながりを持ってWSが開催できていて、2023年には地域の防災リーダーとして活躍できる人材としての育成を目標として活動予定である。 | 神奈川大学「神大の先生での落合紹介」HP https://www.kanagawa-u.ac.jp/professor/details/details_102096.html 2022年に実施したWSの開催報告HP https://www.kanagawa-u.ac.jp/news/details_25803.html |
| S36 | インドネシア・日本での津波防災教育 | 東洋英和女学院大学教授 桜井愛子 | 本発表では、2004年インド洋大津波の被災地インドネシア共和国アチェ特別州バンダアチェ市と、2011年東日本大震災の被災地宮城県石巻市の二つの学校における津波防災教育の事例を紹介します。津波防災教育では、津波避難の3原則を習得することが最も大事ですが、発表で紹介する事例では、教材として現地に残された津波の高さの記録を活用することで地域における被災経験の次世代への伝承へとつながる可能性を示しています。 | 桜井愛子 東洋英和女学院大学大学院HP https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/kenkyuuka/kyoin/s_master/sm_sakurai.html Research Map(桜井愛子) https://researchmap.jp/aikosak 東北大学災害科学国際研究所防災教育協働センターHP 復興・防災マップづくり http://drredu-collabo.sakura.ne.jp/mapping |
| S37 | ○司会・コメンテーター | 関東学院大学教授 渡部 洋 | ||
| S38 | パネルディスカッション | 神奈川県建設業協会 杉原英和 | Ⅰ〜Ⅲまとめ・関東大震災100年)〜これからの100年に向けて〜 | |
| 9月18日(月祝) | ||||
| 第Ⅳ部 神奈川で展開する地域防災活動・地域支援活動 10:30〜12:20 | ||||
| S41 | 「発災直後の行動ゲーム」(J-DAG)の紹介 | 防災塾・だるま 片山 晋 | 大災害が発生すると、直後の1時間が命と家屋財産を失う最も大変な時間帯ですが、ここでの公助は無力であり地域の共助が決め手です。でも、にわか共助では不十分です。私の所属地域では全世帯参加による発災直後の安否確認や不意打ち訓練を実施しており、これをベースに作成したのがJ-DAGです。模擬災害への対処を頭で考え判断し体で行動し、リアルタイムで実践体験するゲームは他になく、J-DAGが全国に広まれば大きく減災に繫がると確信しています。 | 片山 晋 ・ 「横浜市アマチュア無線非常通信協力会・磯子区支部」支部長 HP:http://www.kangaerubosai.sakura.ne.jp ・ 創作/著書:「J-DAG」「防災めくり」「考える防災」等、HP:http://darumajin.sakura.ne.jp |
| S42 | 「空飛ぶ火の見やぐら・ドローン」を使った情報収集 | 一般社団法人 地域防災ドローン・相模原 堀口 眞 | 災害発生時一番大切な事は「正しい情報をいかに早く知ること」である。 共助は「まず自分たちの町を守る」のが最初であるが、ドローンを発災時町内の上空へ飛行させれば、30分以内に地域の大まかな被害状況が把握できる。当法人はこの8月27日に第1回目の実証実験を行った。鮮明な画像が送信された。さらに被害状況をNコード地図 (4桁×4桁の緯度経度入り)に落とし込みデジタル化(情報の共有化)を実証した。 | 「空飛ぶ火の見やぐら・ドローン」を使った情報収集 |
| S43 | 住民主体の災害時情報収集システムの活用 | 東海大学 梶田佳孝 | SNSを利用して災害時に被害状況を報告することは多くの人の役に立ちます。東海大学で開発したDITS (Disaster Information Tweeting System)は災害が発生した際に、被害の状況などをX(旧:Twitter)に投稿し共有することを手助けするアプリです。そのアプリの内容紹介に加え、利用を促進するため、災害時だけでなく、道路損傷箇所等を通報できる平常時での利用などを紹介します。 | https://glocal-dits.u-tokai.ac.jp/ |
| S44 | 災害時の要配慮者支援について~これまでの経験から学ぶ~ | 神奈川県社会福祉士会 理事 横山 昂 | ソーシャルワーカーは、病気や心身の不自由・貧困や加齢など、様々な理由で生活に困っている、あるいは不安を抱えている人が、その人らしく安心して生活を営めるよう、困りごとの解決のために助言や調整を行う相談支援の専門職です。医療や福祉をはじめとする様々な専門家と共に、個人や社会が抱える課題の解決を目指しています。要配慮者が災害時にどのような困難が生じるのか、これまでの経験を基に紹介させていただき、共生・多様性を尊重できるような防災対策をするにはどのような視点が必要なのかを提案したい。 | 公益社団法人神奈川県社会福祉士会 (kacsw.or.jp) 公益社団法人 日本社会福祉士会 (jacsw.or.jp) |
| S45 | まち歩きから考える防災まちづくり | ひらつか防災まちづくりの会 添田睦子 | 関東大震災から100年の今年、ひらつか防災まちづくりの会は結成20年。 振り返れば行ってきたさまざまな活動の中で防災まち歩きの数は少なくない。 まち歩きは 災害対策を考える上でとても有効であるばかりでなく、知らなかったまちや人の魅力などにも気づいていく過程で、地域への愛着が深まったり、声掛け支え合ったりするきっかけにもなるなど、強く優しい防災まちづくりにもつながっていくと考える。 | 「ひらつか防災まちづくりの会」HP |
| S46 | ローリングストックBOX兼ソーラークッカー・簡易感震だるま | 大井町防災まちづくりの会 会長 瀬戸 滋 | 大井町防災まちづくりの会の成り立ちから、活動の中で、自分で身を守り、そして生き抜くために考えたアイディアを、一例としたプレゼンテーションします。 食糧の調理等、自然のチカラを利用した方法をご紹介いたします。 | ローリングストックBOX兼ソーラークッカー・簡易感震だるま |
| S47 | 横浜市緑区における市民による防災意識啓発活動 | まちづくりネットワーク緑 樋口 誠 | 「まちづくりネットワーク緑」は、横浜市緑区のみどりーむ(緑区市民活動支援センター)を活動拠点に、主に緑区に住むメンバー(殆どがだるま会員)が、様々な防災・減災に関する活動を行っています(下記に活動例をしめします)。 *みどりーむ防災・減災講座を毎年開催 *消防署(みどりーむに隣接)見学と、救急救命講座 *出前講座(外国人に対する防災情報の伝達)→防災かるたの作成へ | まちネット緑ニュース第13号令和4年 親子消防署体験メモ 令和5年みどりーむ防災・減災講座報告 |
| 展示 | もし今! 大地震が起こったら... 自主防災会の会長が取るべき行動は。 | QQ防災クラブ 防災士 原田剛 | 自主防災会の会長・リーダーの視点で地震発生直後の行動を検討します。阪神淡路大震災の事例分析から、平時に備えるべき資機材や運用を理解していただきます。 ・自主防災会という組織の特殊性 ・発災直後、自主防災会は機能するのか ・正しい防災訓練とは(間違いだらけの安否確認) ・自主防災会会長の責務 ・日頃の自治会活動は防災訓練の一環 今までの防災啓発本に書かれていない「目からウロコ!のノウハウ」をお伝えします | 自主防災組織会長の役割 防災書籍に書かれていない「目からウロコ!のノウハウ」 |
| S48 | 宣伝コーナー | プログラムのリンク紹介・希望者(101以外で開催している関連団体イベント紹介) | ||
| ○司会・進行: | ひらつか防災まちづくりの会 山田美智子 | |||
| 第5部 神奈川県下の風水害による被災体験から流域の風水害対策を考える 12:30~14:00 | ||||
| S51 | 神奈川県の風水害と防災気象情報 | 横浜地方気象台次長 井上 卓 | 本発表では、神奈川県にも大きな被害をもたらした「令和元年房総半島台風(台風第15号)」及び「令和元年東日本台風(台風第19号)」を例にとりあげ、場所によって自然災害の起こりやすさが異なることや特に留意いただきたい点を説明します。また、緊急時における避難行動の判断や平時におけるタイムラインの検討に必要となる防災気象情報とその発表タイミングについてお伝えします。 | 横浜地方気象台:https://www.data.jma.go.jp/yokohama/index.html 気象庁:https://www.jma.go.jp/jma/index.html 気象庁防災情報(ツイッター):https://twitter.com/JMA_bousai |
| S52 | 2019年台風19号による被害対策とその後の経過 | 広尾学園高校3年 長本吏央 | 2019年台風19号による多摩川の氾濫に驚き、浸水した3箇所の対策の進捗状況を調べました。中学3年から毎年学園祭で発表し、「全国学芸サイエンスコンクール」に入選しました。高校2年では私自身が流域治水に貢献したいと考え、「かながわ緑の大使」となり、上流域の森林整備を行いました。今年は行政と話し合い、高校生以上の若い世代が防災を意識して行動していない現状を共有しました。今日は経過と目標を発表します。 | 資料:2019年台風19号被害対策とその後の経過 2019年台風19号による被害から考える多摩川水害新対策 |
| S53 | 台風19号の被災から考える災害対応 | (一社)神奈川県建築士会 防災・災害対策委員会 河原典子 | 2019年台風19号により、川崎市多摩川流域の自宅は、床上浸水60㎝・準半壊となり、自宅と近隣7件の復旧改修に携わりました。他人ごとではなく、皆さまが住む地域の水害リスクを見直していただくための参考事例としてお話しいたします。災害対応と被災住宅復旧のためには、地域・行政・災害対応関係団体などの「自助・共助・公助」連携と、共に取り組む仲間と、災害対応の仕組みの重要性を痛感して、今の取組みに繋がっています。 | 一般社団法人神奈川県建築士会 【2021.2.26「台風 19 号被害から防災を考える」セミナー】 「防災塾・だるま」HP2022.7 第187 回「防災まちづくり談義の会」レポート |
| S54 | 激甚化する水害と浸水被害住宅の被災後対策について〜「浸水被害住宅の技術対策マニュアル」の紹介と被災地での対応〜 | (公社)日本建築士会連合会 災害対策委員会 (メッセンジャー) 徳島士会 佐藤幸好氏 岡山士会 中村陽二氏 長野士会 湯本和正氏 熊本士会 廣田清隆氏 (進行) 神奈川士会 河原典子 | 岡山、長野、熊本の大きな水害を経験した建築士が、地域の復旧支援活動で得た知見や貴重な体験データを集め、実用的な「浸水被害住宅の技術対策マニュアル」を作成いたしました。自治体職員や技術ボランティア、建築関係者、地域住民や企業の防災担当者など幅広い関係者に活用いただくべく紹介させていただきます。本マニュアルの執筆者である被災地で奔走した建築士が、被災地での体験から実感したこと、教訓や課題、今思う必要な体制づくりなどについて、マニュアルには書かれていない想いや、大切に思うことを語ります。 | 公益社団法人日本建築士会連合会 【災害対応の取組情報】 http://kenchikushikai.or.jp 【1-3:「浸水被害住宅の技術対策マニュアル」(令和4年度策定)】 http://kenchikushikai.or.jp/data/saigai-taiou/202306_info_1-3.pdf 【「浸水被害住宅の技術対策マニュアル」広報チラシ】 http://kenchikushikai.or.jp/data/saigai-taiou/202306_info_1-3_flyer.pdf |
| S55 | 地域をつなぐ地区タイムライン | 「防災塾・だるま」 鷲山龍太郎 | 風水害の危機が迫るとき、誰が、いつから、何をするか。どの段階で避難スイッチを入れるのか。同じマンション内でも、一階住人と二階以上の住人、車の所有者、理事会、管理室等の「タイムライン」は異なる。地区には、多様な団体が存在し、その立地や建物の構造、抱えるリスクによっても異なるタイムラインが複合して「地区ライムライン」になる。これらをマンション、学区で共有した実例を紹介する。また、その統合を試みた研修を紹介する。 | 地域をつなぐ「地区タイムライン」〜公助・共助・自助タイムラインの統合による防災の未来像〜 未来防災NET(個人HP) 各種タイムライン、「綱島の洪水物語」等公開 メイツ大森西管理組合公式HP マンションの風水害タイムライン・地震タイムライン公開 |
| H01 | 全体総括 | 防災塾・だるま 鷲山龍太郎 | ||
| H02 | 閉会挨拶 | |||
| ○司会・進行: | 神奈川県建設業協会 杉原英和 | |||
| ZS2 | クロージングセッション | (中継) | ||