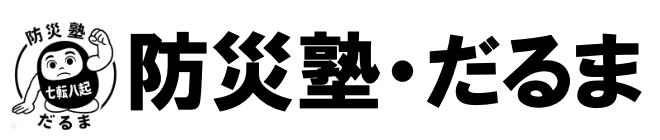防災庁創設への提言 新しい地区防災モデルの提案(2025年度活動方針)
南海トラフ巨大地震・首都直下地震の死者想定を半減する方法

防災関連法規の整合と遵守監督
政府、自治体(地域)、地区一丸の統括する防災庁
災害ボランティアや専門家の「特別公務員」制度化
復興行政における市民参画による高度な調整
人為的要因を含む災害リスクへの対応

共助強靭化
「防災地区」全国一律指定
地区防災計画策定義務(行政支援義務)
地区防災会議→地区防災計画策定
地区防災マニュアル・地区防災教育
地区総合防災訓練実施→津波避難率激増
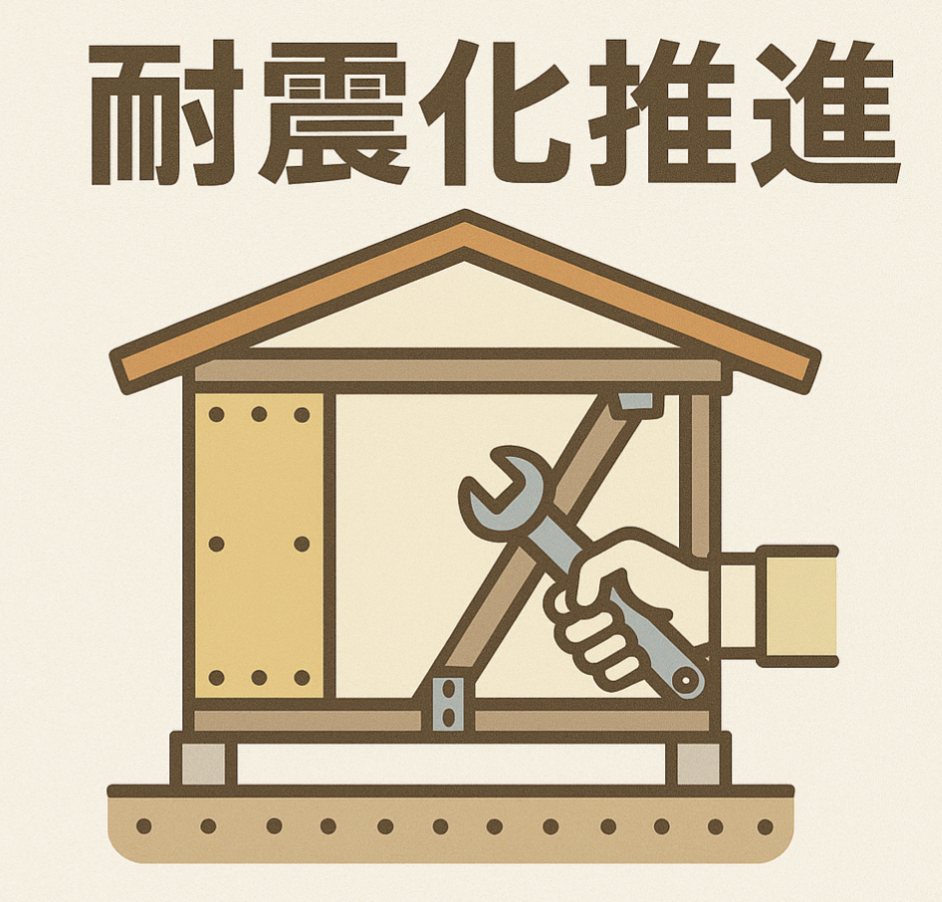
地盤起因の建物倒壊リスク「見える化」
地盤や個別リスクに対応した耐震化推進
高リスクな2000年以前の建築物の耐震政策

SUM基準による物・人配備
(SUM:標準化・ユニット化・モビリティ化)
TKB48による即時被災地支援
(48時間以内のトイレ・キッチン・ベッド)
省庁横断的なインフラ強化と復旧

実効的な避難行動要援護者支援
被災地における女性等人権保護
「ふるさと防災団体」指定と公的支援
「防災・復興コーディネーター」育成
「花博覧会」跡地の防災目的活用

都市部人口の6割を超える
マンション防災力向上
地区防災の主体として連携
※2025年12月6日・13日神奈川大学「防災塾・だるま」連携エクステンション講座開催
「防災塾・だるま」から防災庁創設への市民提言
令和7年6月段階草稿 防災塾・だるま
防災塾・だるまは、地域防災の専門家やボランティアで構成された市民団体です。私たちは防災庁の創設を強く支持し、大きな期待を寄せています。本提言は、防災庁設置準備室が開設された2024年11月で200回に達した本会の防災学習会(防災まちづくり談義の会)を総括し、その後、会員提言アンケート、提言集会、さらなる学習会を経て2025年4月に共通理解化したものです。
この提言は内閣府の方針とアドバイザー会議の意見と対照して、重要な観点をまとめたものです。防災庁設置準備室での慎重な検討をお願い申し上げます。
提 言
1. 「公助」の観点から
(1)防災関連法規の監督
防災庁は、国家的な災害対応の中枢機関として、全ての防災活動を調整し、災害時には迅速な対応を行う。平常時には、乖離している防災法規を統合し、防災関連法令(消防法、災害対策基本法、学校保健安全法など)に示された目標(地区防災計画、要援護者支援、耐震化、学校と地域の連携など)、自治体の地域防災、学校や公共機関、事業所などの「地区」の防災で教育普及、遵守、実現されるようにする。
(2)政府、自治体(地域)、地区が一丸となった災害対応能力の確立
社会の複雑性に対応するため、総力による災害対応能力を高め、事前準備を強化するとともに、自治体任せになっている現行の災害対策基本法を改正し、政府、自治体(地域)、地区が一丸となった官民が連携した実効性ある防災システムを構築する。
(3)災害ボランティアや各種専門家を「特別公務員」として制度化
有事に備え、災害対応に対応できる専門的な人材を育成し、必要に応じて動員できる体制を構築する。(自衛隊の予備役のように)事前登録と研修を制度化し給与も支給する。災害時には被災地以外の人員による救援活動が展開される体制を作る。
(4)SUM基準による即時被災地支援
スフィア基準やTKB48(48時間以内のトイレ・キッチン・ベッド)を実現するために、イタリア式避難所の要となるSUM(同一企画・ユニット化・モビリティ)基準を基に、即時被災地支援システムを全国ネットで実現する。
(5)復興行政における市民参画による高度な調整
防災庁は、地域での関係者間の調整機能を強化し、自治体や関係機関、市民参画による復旧・復興を見据えた防災計画を整備する。
(6)「防災・復興コーディネーター」の育成・配置
事前防災から復旧・復興に至るまで、行政、住民、関係機関の合意形成を支援する「防災・復興コーディネーター」を育成し、各地に配置する。
2. 「共助」の観点から
(1)「防災地区」全国一律指定
全国の自治体に対し、「防災地区」の指定を義務づけるため、災害対策基本法を改正する。
(2)「地区防災計画」策定と「地区防災会議」開催
各防災地区において、行政、学校、住民、事業所、医療機関、消防団などが参加する「地区防災会議」を行政主導で年1回以上開催し、標準項目に基づいた「地区防災計画」を策定する。計画には、災害リスク、避難行動、復旧・復興、役割分担、専門家活用、各主体・行政の責務などを明記する。
(3)「地区防災マニュアル・地区防災マップ」の策定
地区ごとの防災計画に基づいた防災教育の一環として、「地区防災マニュアル」および「地区防災マップ」を策定します。これらは、全国統一基準に従い策定されるものであり、AI等の先端技術を活用した策定支援システムの導入を推進する。
(4)地区総合防災訓練の実施
災害防災計画・マニュアルに基づいて住民と関係団体が参加する地区総合防災訓練を行う。学校は特別活動として防災教育に参加する。
(5)実効的な避難行動と要援護者支援
災害関連死を予防するため、地区防災計画の中に要援護者支援を規定し、行政主導で個人情報保護法に配慮した標準的支援体制を確立する。安否確認や避難支援の実効性を高める。
(6)「ふるさと防災団体」の指定と公的支援
市民活動や防災教育の普及を促進する地域で実際に活動する団体への経済的支援を法制化する。
3. 「自助」の観点から(高齢化社会に対応した公助の自助支援)
(1)地盤による建物倒壊リスクの「見える化」と耐震化推進
地盤ハザードマップの高精度化により、地盤情報と建物倒壊リスクの「見える化」を進める。
(2)「常時微動」を使用した地盤調査やボーリング調査データの共有により、詳細な地盤調査と優先的な耐震化推進
地盤が脆弱な地域や要支援者世帯を優先対象とし、住宅の耐震化を強力に推進する。
(3)2000年以前の建築物の耐震診断と低価格耐震工事の推進
2000年以前に建てられた建築物の耐震診断と、地盤条件に基づく優先的な耐震化を明確にするこことにより、一部地方で実績がある低価格耐震化、地盤改良、家具転倒防止・整理などの対策を優先順に推進する。
4. 「新しい災害課題」の観点から
(1)省庁横断的なインフラ強化と復旧
上下水道等老朽化したインフラ、ITを含む新インフラに対して省庁横断的な調整を強化し、災害時の被害を最小化する。
(2)人為的要因を含む災害リスクへの対応
感染症や原子力災害など人為的要因に備えた対策を強化し、事業所の地区防災会議への地区防災計画の策定に参画することを明確化する。
(3)「国際園芸博覧会(EXPO2027)」跡地等の防災目的活用
横浜市旭区・瀬谷区にわたる広大な敷地を活かし、体験型屋外訓練広場を常設化し、さらに、防災庁を中心とした自衛隊・警察・消防・自治体・地域住民による連携訓練の拠点にする。
参考例【災害対策基本法の一部を改正する法律案(防災塾・だるま提言反映版)】
【提案理由】現代社会は複雑でグローバル化が進む中、南海トラフ地震や首都直下地震など大規模災害の懸念があります。従来の災害対応には限界があり、人命と財産を守るためには柔軟な対応と人材育成が不可欠です。1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災でも災害対応の遅れが見られました。事前復興計画の準備の不十分さや住民との合意形成も課題となっています。防災庁設置の機会に災害対応力がある仕組みづくりが期待されます。
本法案は、防災塾・だるまからの提言を受け、次の4点を柱とするものである。
1. 公助の強化として、防災庁的組織の新設による統括機能、防災法令遵守監督体制の構築
2. 共助の強化として、全国一律に防災地区を指定し、地区防災計画・教育・訓練を法制化
3. 自助の促進として、脆弱地盤等における住宅の耐震化支援と情報公開義務
4. 新たな災害課題への対応として、専門人材制度とコーディネーターの配置、インフラ調整の強化等
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する提案
第一条の次に次の一条を加える。
(防災行政の基本理念)
第一条の二
国は災害対応の中枢機関として防災庁を設置し、防災に関する省庁及び各種法令を整理、統括し、全ての防災活動を調整して迅速な対応を行う。
第五条を次のように改める。
(国の責務)
国は、防災に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、防災庁を中心として関係行政機関を統括し、地方公共団体、民間団体、住民との連携を図る。平時においては防災地区の指定、法令遵守の監督及び実効性ある防災体制の整備を行わなければならない。
第八条の三として次の条を加える。
(防災法令遵守監督制度)
第八条の三
1 防災庁に「防災法令実現推進室」を設置する。
2 推進室は次に掲げる事務を行う。
一 地方公共団体等における法令遵守状況の監視及び評価
二 技術的助言及び財政的支援
三 全国防災実施状況報告書の年次作成及び公表
(消防法、災害対策基本法、災害救助法、建築基準法、耐震改修促進法、学校保健安全法等)
第四十二条の次に次の条を加える。
(防災地区及び地区防災計画)
第四十二条の二
1 市町村は、文教学区等を基本とした「防災地区」を指定し、防災地区ごとに「地区防災計画」を策定しなければならない。
2 国は、防災地区の指定に関する基準を定め、必要な技術支援及び交付金配分を行う。
3 地区防災会議を年1回以上開催し、災害リスク、避難、役割分担、支援体制等を計画に明記する。
第四十二条の三として次の条を加える。
(防災教育及び防災訓練)
第四十二条の三
1 市町村は、地区防災計画に基づき、住民・学校・事業所を対象とした「地区防災マニュアル」及び「防災マップ」を作成する。
2 住民等による地区総合防災訓練を年1回以上実施し、学校教育における防災教育の充実を図る。
3 市町村は、防災活動を行う団体を「ふるさと防災団体」として指定し、財政的支援を行うことができる。
第五十条の二として次の条を加える。
(住宅等の耐震化支援)
第五十条の二
1 国及び地方公共団体は、地盤の脆弱な地域及び高齢者・障害者世帯に対し、耐震診断及び改修を優先的に実施するための制度を整備する。
2 2000年以前に建設された建築物については、耐震診断の義務化を図る。
3 地盤情報及び耐震基準に関する情報公開を義務づけ、不動産取引時の明示を求める。
第五十三条の二として次の条を加える。
(専門人材の育成と任用)
第五十三条の二
1 国は、災害ボランティア及び災害対応に従事する専門家を「防災特別公務員」として登録・研修を義務づける制度を設ける。
2 復旧・復興を円滑に行うため、「防災・復興コーディネーター」を育成・配置する。
附則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の二及び第四十二条の三の規定は公布の日から一年以内に施行するものとする。
| 本提言が、防災庁の設立とともに、より実効性のある防災体制の構築に寄与することを心より願っております。 令和7年5月7日 「防災塾・だるま」会員一同 塾 長 鷲山龍太郎(防災士 元小学校長) 名誉塾長 荏本 孝久(神奈川大学名誉教授) |
防災まちづくり談義の会200回記念を迎えて
2024年11月、「防災まちづくり談義の会」は記念すべき200回を迎えました。これを機に、会員アンケートや有志による発表を通じて過去の活動を振り返り、その叡智を集約する機会としました。また、これまでの歩みを振り返るとともに、今後の防災まちづくりの展望を共有する貴重な場となりました。
防災庁設置準備室の設置と重なるタイミング
奇しくも同じ2024年11月、石破政権の提唱により「防災庁設置準備室」が発足しました。
その基本方針には、「防災塾・だるま」の理念と通じる部分も多く、大きな期待を寄せています。
今後の展望
「防災塾・だるま」では、地域での活動、被災地支援ボランティア、専門家による災害への多角的な考察など、多様な視点から防災に取り組んできました。今後もその知見を集約し、防災庁設置に向けた具体的な指針に反映させていきたいと考えています。
その一環として、2025年4月には提言書を定例会にて取りまとめ、合意形成の上、防災庁設置準備室に提出する方針です。
こうした活動を通じて、「防災まちづくり談義の会」200回分の学びが、2026年の防災庁創設に向けた具体的な提言として結実することを目指しています。
談義の会200回総括から防災庁設置準備室への提言とりまとめの歩み
| 期日 | 取り組み | 成果・資料 |
| 2024年10月〜11月 | (本会)談義の会200回振り返りアンケート実施 | アンケート集計結果 |
| 2024年11月1日 | (内閣府)防災庁設置準備室開設 | |
| 2024年11月15日 | (本会)第200回防災まちづくり談義の会開催 | チラシ アンケート結果・講演会レポート 防災まちづくり談義の会200回アーカイブ |
| 2024年12月 | (内閣官房防災庁設置準備室) 政府かにおける防災施策・体制の現状等について 各省庁からこれまでの取り組みやこれからの取組みを共有 | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bousaichou_preparation/dai1/siryou1.pdf |
| 2025年1月30日 | (内閣官房) 防災庁設置準備アドバイザー会議 | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bousaichou_preparation/index.html |
| 2025年2月22日 | 防災庁創設への市民提言を考える 基調講演+パネルディスカッション 荏本名誉塾長から勉強会等助言あり | チラシ 防災塾・だるま会員からの提言一覧 内閣府方針・アドバイザー会議提言と本会会員意見の対比一覧 |
| 2025年3月21日 | (本会)防災庁設置に向けた臨時集会 | 3月21日臨時集会原案 |
| 2025年4月17日 | (本会)定例会にて「防災庁防災塾・だるま提言書」決議 | 会員アンケート・メール等を踏まえた臨時集会取りまとめ案(4月17日定例会に提案) |
| 2025年4〜5月 | (本会)「防災塾・だるま提言書」を防災庁設置準備室に提出予定 | 防災庁設置準備室への挨拶文 防災塾・だるまから防災庁創設への市民提言250506 |
2025年2月22日 第202回防災まちづくり談義の会防災庁創設への市民提言を考える
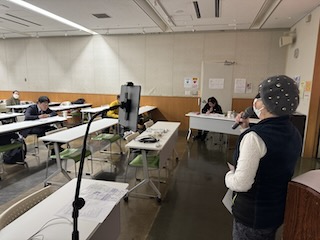
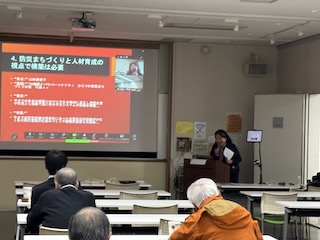
防災市民団体の実践からの提言
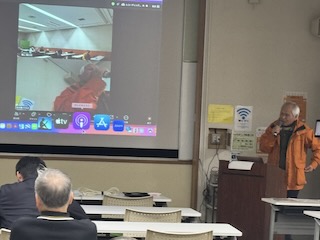
自主防災組織の実践から提言
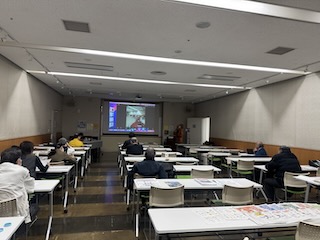
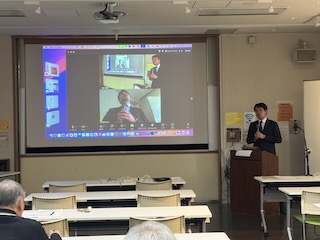
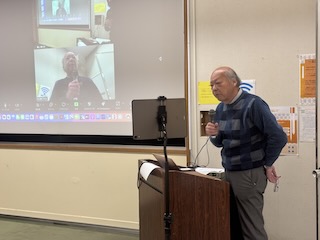
会員の熱い提言が発表される 古川総務大臣政務官秘書様からのご挨拶 荏本名誉塾長からの提言と助言